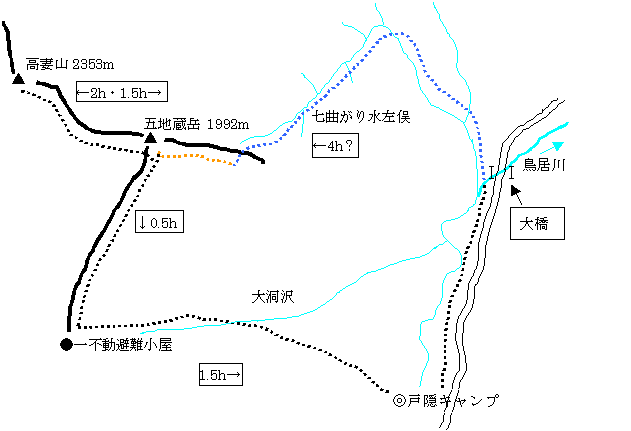日比谷草鞋つける。
47' 03" 4
05' 48" 5
46' 59"
05' 51"
宍戸さんら高妻山隊と合流。
予定では 3:20 起床、4:10頃出発であったが、雨の音に出鼻をくじかれた。
時間通りには起きたが、朝食をとりながらしばらく様子を見ることにする。
日比谷さんの携帯やノートパソコン等で気象情報を集めてみるがまだ梅雨前線
の端が東日本にかかったような状態で、降っても降らなくてもおかしくない
感じである。そのうち雨は霧雨のようになり、 5:05 に出発した。
キャンプ場から舗装道路を大橋まで歩く。雨はほとんどやみ、前方に黒姫山
の裾野が見えるが、上の方は霧の中である。大橋は、車だと気付かずに通り
過ぎてしまいそうな、特徴のない橋であった。ここからゲートを越えて林道に
入る。10分ほど行くと沢に下りる道があったので、ここから沢に入る事にする。
この林道と沢の連絡路はかなりはっきりした踏み跡で、渓流釣りの人が使う
のであろうか?日比谷さんはここでワラジをつけた。
ロック&ブッシュの記事等からしばらくは河原歩きをするものと想像して
いたが、実際は多くは流れの中を行く感じであった。大洞沢の下部とよく
似ているが、それよりは明るい感じか。しばらく行くと釣り客が一人いた。
沢登りの登山者と釣り人では利益の相反するものだが、やはり川からは
上がって欲しいと言われた。しかし川から上がれば薮の中であり、ここから
薮漕ぎをするわけにはいかない。
何回か沢が曲がった後、左俣に入る。しばらくは同じような渓流歩きである。
少し行くと、たびたび左手(右岸)に土のあらわになった崖が見えるように
なる。火山体積物であろうか。沢が蛇行しているので、その度に左に曲がり
出すゴルジュのところまで来たのかと期待するが、そうすぐには着かず、
歩き出してから一時間の所で休憩。高度計などの情報から、さすがにゴルジュ
直前であろうと判断する。歩き出すと実際沢は左に曲がり出し、遡行図にも
ある右手からの二本の合流を確認する。確かに以前の開けた渓流に比べれば
沢はせまくなってきているが、ちょっと「ゴルジュ」とは認め難い。ただ
傾斜が出てきたせいもあって大分沢らしくなって来たのが楽しい。遡行図
で「?」となっている左手からの沢も確認した。薮の中の沢で、水流は確認
できない。
しばらくしてトップを歩いていた井坂君が止まる。合流があるが、すぐ上で
二手に別れたものがまた一緒になっているようにも見える。私(横山)が
20m 程先まで行って、別の沢である事を確認する。地図を出し、最終的に
ここが F2 と F3 の間の 1:1 の二俣であると判断し、左の流れに入る。
この二俣は、左から急な流れが合流するように予想していたが、実際には
急な流れが一旦少しゆるやかになり、同じような流れが合流していた。
下から見ると正面(右側の流れ)の奥の傾斜の方が急に見えるが、確かに
改めて地図を見るとそう見えてもおかしくないようだ。(国土地理院の地図と
いうのは正確なものだ。ブッシュ&ロックの遡行図が正確なのにも驚く。)
この先も地図と日比谷さんの GPS の助けも借りて位置を確認しながら進んだ
が、結局一度も道を間違える事はなかった。
ゴーロ、といっても開けたゴーロではなく、林間の石のごろごろとした
急登(もちろん水流あり)をしばらくいくと、F3 に着いた。ここはこの沢で
唯一滝らしい滝であろう。ブッシュ&ロックの記事についていた写真では、
水流は主に大きな岩の(下から向かって)左側であったが、今は主に、
岩の上の、チョックストンに近い方から水が落ちている。岩の上の石や流木で
いくらでも変わってしまうようだ。以前から日比谷さんの鞋がずれたりして
いて、その度に直していたが、ついにここで交換する事になった。どうも脇の
「乳」の所が切れてしまうようだ。ここの所は岩角などにあたることが多い
だろうし、この部分だけ補強してあればもう少し持つのではないか、などと
話していた。
この後傾斜はゆるくなり、1596m ピークの方から来る沢を分ける。森の
中で、ゆるやかに交わるという感じだ。右から来る小さな沢を越えた所で
位置確認も兼ねて休憩、そのまま昼食となった。昨晩炊いた米をそのまま
持ってきたので、まずそれを食べ始めたが、わずかな漬物以外おかずが
ほとんどなかった。(皆チョコレートやビスケットは持っていたようだが)
残るのではないかと思っていたが、以外と空腹であったようで、話しながら
食べているうち平らげてしまった。
ここから先は間違えそうな分岐はなく、沢が終ったら薮の薄い所をめがけて
行けばいい。水は大分少なくなって、なめのようになっている所があるかと
思うと、伏流になってしまったりする。途中振り返ると下の方がよく見える
所があった。いよいよ水はなくなり、薮に突入して行く。傾斜が急になると
ともに根曲がり竹の密度が増し、猛烈な薮となる。足元が滑りやすいのにも
気を使う。鞋の日比谷さんは大変そうだ。稜線はまだか?稜線はまだか?
もうそろそろだろうという頃、トップの井坂君から「道がある」との事。
最後に壁のような薮を突破すると、牧場の方から五地蔵山の頂上に向かって
尾根筋をずっと刈り込んであるのに出会った。どこからどこまで刈ってある
のだろう。なんのために?とりあえず、渡りに舟という事で、休憩し、鞋や
渓流シューズから登山靴に履き変える。振り返ると正面に飯綱山、今まで
登ってきた方には梢の向うに黒姫山の中央火口丘(小黒姫、または御巣鷹山)
が見えた。結局ここから五地蔵山(六弥勒)の頂上まで刈り込みは続いたが、
傾斜が急だったこともあって、一時間ほどかかった。しかし、刈り込みの中で
横を見るとびっしりとした笹薮で、もし刈り込みがなかったらと思うとぞっと
する。
13:10 になって明らかに地図の五地蔵山の頂上となっている地点に着いた
が、登山道が見当たらない。ところが人の声がするようだ。これは地図が
間違っていて、登山道はこのピークを捲いているのではないかなどと言って
いたが、よく見ると、刈り込みを、そのままピークを越えて数 m 下ると
登山道と合流していた。その登山道を戻ると、さっき居た所のすぐ裏に
六弥勒の標識と祠があった。ほんの 1m の薮の向うが見えなかったのである。
やはり地図は正確なのであった。
ほんの少し休んでいる間にも何人もの登山者が通り過ぎて行く。さすがは
週末の一般道だ。高妻山が百名山になっているせいでもあろう。我々が
五地蔵山に着くまでには、釣り客一人に会っただけであった。この六弥勒の
祠のピークの西隣のピークからまたパーティーが下りてくるのがよく見える。
高妻山から下りてくるパーティーであるが、見ているとどうも、その中の
一人の女性はどうも宍戸夫人であるようだ。とするとあれが山本さんで、
矢頭さんで、ということで、日比谷さんと井坂君がコールをかけ始める。
ということで、20期宍戸さんら高妻山隊と合流する事となった。
この後、後から来る女子中学生(高校生?)三人組などいくつかのパーティー
に先に行ってもらいながら、ゆっくり一不動、大洞沢経由で下りたが、今回は
二年前と違い、雷も濁流も、雨の中二時間も沢の水が引くのを待つ事もなく、
無事牧場に着く事ができた。牧場では、馬が飼葉桶の中の、何かプラスチック
の塊のように見える物をさかんに嘗めていたが、あれは何だったのだろう。
こうしてキャンプ場に帰ったのは午後五時を大分過ぎた頃だった。
45B 横山雅彦 記